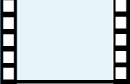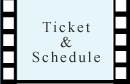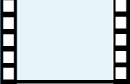|
今公演『最後の1フィート』は2005年最初の松本陽一作品になる。松本自身初の「隠れ宿公演」(アトリエ公演)での脚本・演出。さまざまな意味で新たな試みが期待される今公演である。台本執筆も佳境に入り、稽古も本格的に始動した今、松本陽一は何を思うのか。
まずはタイトルの『最後の1フィート』について聞いた。
 「実は映画学校の学生だった頃に勉強がてらに書いた作品のタイトルなんです。どこにも日の目をみることもなく、書き上げてもなく、終わってしまった作品のタイトルです。映画の話を舞台でやろうかなと思ったときに、ふと思い出してタイトルをつけちゃったんですよ。僕はわりとタイトルから先につけちゃうんです。中身はそれからみたいな。以前は完成させられなかった作品なのでね、今回は完成させようかなと。」 「実は映画学校の学生だった頃に勉強がてらに書いた作品のタイトルなんです。どこにも日の目をみることもなく、書き上げてもなく、終わってしまった作品のタイトルです。映画の話を舞台でやろうかなと思ったときに、ふと思い出してタイトルをつけちゃったんですよ。僕はわりとタイトルから先につけちゃうんです。中身はそれからみたいな。以前は完成させられなかった作品なのでね、今回は完成させようかなと。」
今回の「最後の1フィート」はサブタイトルにもあるように~一篇の映画を巡る3つの物語~とあるが、一つの作品の中に3つの物語、これは初の試みである。以前からこの構想があったと語る。
「順序は色々あるんですが、先に“隠れ宿公演”って企画があって、じゃあ何やろうって思ったときに、“小さな物語”をやりたいなと。僕の作品は大人数が出てくることが多かったんですが、それを隠れ宿でやったらうるさいだけかなと思って。2、3人でしゃべっているイメージだったんですよ、狭い空間でね。そういう作品ができたらいいなって。それで一つの出来事を色んな立場の人からみたら面白いなと。例えば刑事ドラマだったら、刑事はヒーローっていうか、観客は刑事に感情移入しますよね。そこにやってくる新聞記者が悪者だったり。逆に新聞記者のストーリーだったら刑事が悪者になったりする。だから目線を変えたら、一つのことでも色んな見方があるんですよね。そんなふうに一つのテーマに対して、色んな角度から見たお話をつくったら面白いと思ったんです。そのテーマを何にしようと考えたときに“映画”がでてきて、そういえば昔書いたなって、あの作品が浮かんできたんです。『最後の1フィート』っていいなって。」
今公演の3話を通じて芯になるのは、とある1本の映画である。3つのシーンで、各登場人物たちがそれぞれの視点でその映画に関わっていく。
「一つの地味な映画なんですけどね、その映画を通じて出会った人たち。その映画がなかったら出会わなかった人たち。そういう設定で描きたかったんです。
あとね、映画をテーマにするにあたって、映画からできるだけ離れたかった。え、こんな人が関わるのみたいな。普通に関わる人たちって言えば、監督とかカメラマンとかプロデューサーとかですよね。そうじゃなくて、もっと全く無縁そうな人が関わってきたら面白いかなと、漫才師とか女子高生とか。もちろん映写技師とか普通に関わる人もいますけど、それ以外に映画に無縁な人たちが関わってきたら面白いかなって。」
今回の作品では映画を題材にしているが、確かに、様々な肩書きをもったキャラクターが多く登場している。その意外性もまた松本のプロットであるようだ。
 「関わってる人もいますけどね。まだ知名度は低いですが、フィルムコミッション(*1)とか。最近活発になってきた活動団体なんですが。そういう人も出てきてます。 「関わってる人もいますけどね。まだ知名度は低いですが、フィルムコミッション(*1)とか。最近活発になってきた活動団体なんですが。そういう人も出てきてます。
基本的に好きなんですよね、全く知らないもの同士が顔を合わせるっていうのが。知らないもの同士が火花散らすみたいなね。火花っていうか化学反応を起こすって言ったほうがいいかな。第3話なんて、ありえない3人組を作ってからその化学反応ってどうなるかなって思って書いてます。」
| |
*1:フィルムコミッション【film
commission】―映画のロケーション撮影の際に発生する業務を撮影者に代理して行う機関。撮影場所を使用するための申請,地元住民との調整,宿泊施設・警備会社・エキストラの手配などを行う。 |
先にも本人が語るように、松本陽一自身、映画監督を目指し映画の学校で学んでいた時期がある。松本の芝居の基盤になったともいえる映画学校。その体験は今公演にどう影響しているのだろうか。
「大船撮影所ってもう今はない撮影所の中にあった学校なんですよ。普段それこそ松竹映画の大御所がいっぱい出入りしているような。だからそういった厳しさとか面白さを目にすることはありましたね。今回の話の中でも映画について語るシーンなんかは学校時代の友人が実際現場で体験したことを聞いて書いたりしています。実際のフィルムコミッションってこういう人だよとか。
例えばカチンコ鳴らすだけでもすごいこだわりがあって、撮影現場に入った時に聞いた話なんですが、カチンコってありますよね。シーン撮影の最初に「本番、よーい、カチン」っていうやつ。カチンコって一番下の助監督が鳴らすんですけど、僕の先輩がカチンコを鳴らす練習をしているときに、現場の助監督のチーフの人が厳しく指導してくれたらしいんです。あのカチンって音が1秒24コマのうちの3コマにおさまらなくてはいけないとか、2度打ちになっちゃいけないとか、役者さんの目の前で叩かなくちゃいけないけど役者さんの邪魔になってはいけないとか、それにもセンスがいるんだそうで。深いなって思いましたよ。」
“1秒24コマ”つまり1コマ=約0.04秒。『一瞬』の中に色んなこだわりが重なりあっているのだ。
「編集もね、ほんとにミクロの世界で3コマ5コマくらいにもこだわるんですよ。2時間もある映画で、1秒24コマの中の5コマにね。ちなみに今回のタイトルに使っている「1フィート」って1秒無いんですよ。実際に2時間映画は何万フィートですから。だから「1フィート」って本当に一瞬なんです。でも編集作業をすると、その一瞬に色んなものが詰まっているんですよ。カチンコもそうだし、役者さんの表情もずっと追っていけば一コマ一コマが大切になってくる。その一コマの前で切るか後ろで切るかで、作品がぜんぜん変わってきたりね。役者さんがセリフを言った後の余韻を何コマ残すとかね。
で、そういうのが今回のタイトルになっているんです。最後のたった1秒足らずのちょっとした部分でも色んなものが入ってて、それによってくすんだり、輝いたりもするんだよって。」
これまでのインタビューで今作品「最後の1フィート」が出来るまでの過程が見ることができた。一つのものを創り上げる中には、舞台や映像のように表に映し出されるものの他にも、それを創る側にも様々な物語があるようだ。
次週は稽古の様子、隠れ宿公演などについてお話を伺います!
どうぞお楽しみに!
Vo.2へ
松本陽一プロフィール
|