第二章第一節 「酒樽を盗んだ男」
―盗人タジムとその仲間―
|
ソマテの盗人
この物語には、僧侶、武人、砂漠の民と様々な人種が登場するが、それらはすべて一人の男を中心に回転する。盗人タジム、である。
図1
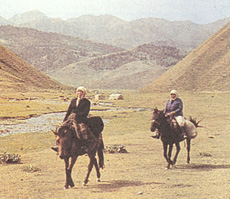 |
契丹人とは、遊牧民といった意味(だと思う)。
辞書にも載っていない言葉を脚本家はどこか
ら引っ張ってくるのか。ちなみに写真は
キルギス人。 |
ソマテ(注1)に生まれ、親に仕込まれて盗人になったというタジムが、酒樽を盗んだ罪で刑場に引き出されてくる。物語はここから始まる。この時代(注2)の盗賊の資料はあまり無いが、この職業はいつの時代もあまり変わらないようである。後になってカナとシャッポが、タジムに契丹人(図1)のキャラバンから天幕(注3)を盗んだという武勇伝を聞かせるというくだりがあるが、そこから見ても、盗賊という職業の説明は、圧制に苦しめられている民衆の中にあっても自由奔放に生きている人種、と言っても良いようだ。
カナは若い娘、シャッポは少年(注4)。この二人が同じソマテの生まれでタジムと兄弟のように育った仲間である。
注1―前回までのおさらい。ソマテとはマサロに隣接する狭い地域。サラガヤの侵攻によってサラガヤの領地となった。つまりマサロ人同様、サラガヤ人にいじめられている民族。
注2―何度も記したように、この作品は架空の世界の話なので、「この時代」といってもはっきりとした訳ではない。
注3―テントのようなもの
注4―少年だからといって子役が登場するわけではない。では誰が演じるのか、ピーターパンとかと同じ方法です。
英雄との出会い
図2
 |
実際に出土されたタジムが
聖殿から盗んだとされる酒樽。
1974年、考古学者ラビーンが
現地で撮影。 |
タジムは刑場で死刑を宣告される。この時代(注5)は、罪を犯せば即死刑といったイメージがあるが、酒樽(図2)を盗んだだけで死刑というのもあまりに厳しい法である。実はそこには権力者側サラガヤの思惑が隠されていた。
刑場で死刑を宣告されたもう一人の男、マサロの英雄テンガローネ・ラクサーダ(注6)。彼は民衆の指導者であり、虐げられているマサロ人から絶大な支持を受けていた。当然権力者たちが黙っているはずもなく、だからこそ死罪を受けることとなるのだが、ただ処刑するのではなく、身分の卑しい盗人と共に処刑することでラクサーダの名を辱めようと権力者は考えたのだ。
刑場で兵士の一人が謳う。
| よいか、耳あるものは聞け。マサロのラクサーダは盗人と並びて刑に処される。この男は神でもなければ聖者でもない。 |
そんな思惑が、タジムとラクサーダを引き合わせることとなり、そしてそれが、
一人の盗人の運命を大きく変えることとなる。
注5―くどいようだけど、架空の話。
注6―何故か台本には彼の名前のみフルネームで書かれている。ということでタジムの上(下?)の名前は不明。
|
次回は、第二章第二節「対立の構図」
―祭司長ラビナス、千騎長ハンガス―
です、お楽しみに。 |

|