|
最終話 「張り詰めた空気」
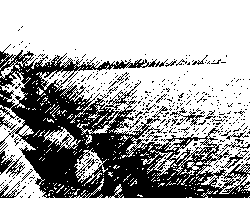 午後2時15分。稽古場の休憩室の窓から、松本はさらに激しさを増す降雪を眺めていた。 午後2時15分。稽古場の休憩室の窓から、松本はさらに激しさを増す降雪を眺めていた。
「敷島さん、見事な推理でしたが、私は連れてきた赤ん坊をただ漫然と育てた訳ではありません・・・」
稽古場から聞こえてくる天宮良蔵役の小沢の声を聞きながら、松本は今作『桐の林で二十日鼠を殺すには』の台本をペラペラとめくった。メンバー達はそれぞれが二階や地下に散っていて、休憩室は松本ひとりだった。
「知ってるかい。運転手にも任されたルートで序列があるんだよ。腕が良くてさ、見てくれもいい奴だったら・・・懐かしいな」
バスの運転手長本の台詞を呟きながら、松本は97年の再演の時のことを思い出していた。あれから4年、デビュー作となった長本役から、今度は記者敷島役となっての再々演である。
「今回は早めに台詞を入れるかな」
と台本の敷島の出る部分をめくった時、聞き慣れた携帯の着信音が休憩室に響いた。
「マイムマイムを着信音にするなんて、変わってるよなカズさん」
と松本はその着信音を聞き流していたが、一度切れてはまた鳴り、また切れては鳴るその携帯に松本は苛立った。
「何だよ、せっかちな人だな」
4度目の着信音が鳴った時、松本はその携帯を手にした。
「はい、もしもし」
「・・・・あ」
携帯の向こう側で男の慌てた声が聞こえた。
「ああ、すいません。私、小沢と一緒に芝居やってる松本というものです。今、小沢は稽古中でして・・・」
「松本、さん?」
男は聞き返した。
「はい・・あの、小沢は今、手が離せないものですから、もうじき稽古が終わると思うのですぐかけ直させますが」
「・・・そうですか」
やけに暗い声だな、と松本は思った。
「あの、急ぎでしたら何か伝言しますけど」
と松本が尋ねたが、相手は何も言わなくなった。
「あの・・・」
と松本が不審に思いながらも聞き返した時、携帯の向こう側から重い声が聞こえてきた。
「・・・じゃあ、伝言してもらえますか」
「あ、はいはい、ちょっと待ってくださいよ」
と松本はペンとメモするものを慌てて探した。傍にあったペンとさっき開いていた台本を手にする。
「はい、どうぞ」
「・・・・小沢さんに伝えてください。五井沢村のバス停が見たいのなら・・・」
「ちょっと待ってくださいね」
と松本は台本にペンを走らせる。
「ごいさわ、むら、のバス停、が、見たい・・・」
松本の手が止まった。
「え?・・・すいません、これはどういう意味、ですか」
五井沢村といえば、この作品に出てくる地名だ。松本は思わず聞き返した。丁度、稽古場から小沢の声が聞こえてくる。
「今の私は、寒村の田舎医者。肩書きも、五井沢村村営病院の嘱託医です・・・」
松本はもう一度聞きなおした。
「ええと、すいません。五井沢村っていうのは・・・」
「いいから、その通りに伝えてください」
携帯の向こうから少し苛立った声で、その男が言った。その声に松本は、何やら尋常ではない警戒心を覚えた。この人は、何かおかしい・・・。
その時、その男の声の後ろで響いてくるもう一つの声を松本は聞き逃さなかった。
「嘱託医といっても、私が担当する・・・」大きな声が遠くから響いている、そんな感じだった。松本は耳をすませた。
稽古場でも丁度同じ台詞が聞こえてくる。「・・・嘱託医といっても、私が担当するのは数人の老人だけです・・・」稽古場から聞こえてくる声と、携帯から聞こえてくる声がステレオのように松本の耳に入ってきた。
「どういうことだ・・・。そうか、この人は稽古場のすぐ裏から電話してるんだ・・・」
と松本は思った。携帯からは、なおも稽古場での小沢の声と、苛立ったその男の声が聞こえてくる。
「あの、すいません。つかぬ事をお聞きしますが、今どちらにいらっしゃいますか?」
自分の質問にその男は動揺したように松本には聞こえた。
「いいから、言った通りに伝言してください」
その答えに松本は一瞬考えた後、その男にこう答えて電話を切った。
「ちょっと待っててくださいね」
松本は台本を置いて、ゆっくりと立ち上がった。
× × ×
「まさか、テレビ中継に映ってたなんてな。おかげでホタルおじさんにも会えたって訳だ」
山の手線の車内で松本は言った。隣には宮岡が座っている。
「そうよ、五井町から横浜までどうやってあの雪の中行ったのか。余計にこんがらがったんだから」
「でも、彼の顔を見た時に正直驚いたよ」
と松本は、まるで友人のことを話すかのような口調で言った。
「青柳、のこと?」
「うん、だっていつも稽古場に配達に来てた人だろ。カズさんの知り合いだった事も知らなかったし。あの雪の日、外に出て稽古場の裏手に回ってみたら、スカイラインが停まってて中に彼がいたんだ。やあ、久し振り、とか言っちゃったよ」
と松本は笑った。
「で、いきなりスタンガンを喰らっちゃったって訳」
「ああ、気がついたら海ホタルにいた。最初は何が起こったのかさっぱりでね。ホタルおじさんにオイルを分けてもらったけど、結局そうこうしてるうちに車が動かなくなりそうだって彼が言うんで、じゃあ俺んち来いよ、鍵が無くても入れるんだぜってな。それで横須賀への通り道だったあの横浜の家に滞在したって訳だ」
確か森口が同じような言い方をしていたなと、宮岡は思い出していた。松本がどこまで冗談でどこまで本気で話しているのかが分からなかった。
「それは、あのバス停が物置にあったから?五井沢村のバス停が見たいって書き置きから、誰かがそのバス停の存在に気付くんじゃないかって思ったんでしょ」
そう尋ねた宮岡の顔を見て、松本は笑った。
「でも、誰も気付かないで、偶然見つけたんだろ。森口が。あいつ結局公演は観に来れなかったんだよな。間が悪いっていうか、何て言うか」
「でも今日退院よ。いろいろと彼も役に立った訳だし、退院祝いに何かおごってあげれば」
と宮岡は笑った。松本はようやく真顔になって答えた。
「嫌だ」
× × ×
 「もう一週間早ければな」 「もう一週間早ければな」
もう葉桜に変わり始めた並木を歩きながら、富沢は小沢に言った。
「でも、先週は公演中だったからな。結局花見も出来ずじまいか」
と並木を見上げる富沢の横で、小沢は桜並木から広がる母校の大学の構内を眺めていた。そこには賑やかな音を立てながら黄色い大きなテントが立っていた。
「謙ちゃん、あんな風に僕と彼も芝居をやってたんだ」
「青柳、か。確かカズさんの後輩だったよな」
「うん、一つ下だったけど・・・」
富沢は話題を変えるように言った。
「テント芝居か。俺もやってみたいな。臨場感たっぷりだろうな」
小沢は微笑んで、立ち止まった。
「・・・彼とのテント芝居はいい思い出だったよ。でも彼には思い出で片付けることは出来なかったんだ・・・」
そう言って小沢は、黄色いテントに向かって歩き出した。
× × ×
針金を押したり引いたりしながら森口は、黒のハコスカのトランクを開けようと悪戦苦闘していた。
「・・・死体なんか出てくるはずは無いよ。そうだ、犯人の持ち物とかそういった重要な手がかりが出てくるんだ。そうに違いない」
半ばやけになってトランクをがんがんと叩いた時、森口は背後に人の気配を感じた。
「誰だ!」と振り返る間もなく、森口は後頭部に激痛を感じた。抵抗しなくては・・・。そう思いながらの意識が遠のいていく。
森口は振り返った。一人の男が手に大きな石を持って立っている。どこかで見たことある顔だ、確か稽古場の玄関で・・・。
「くそっ、松本さんはどこだ!」
遠のく意識の中で、森口は力を振り絞って、その相手に掴みかかった。
「離せ!離せよ!」
森口の火事場のバカ力に圧倒されて、その男も必死で抵抗する。
「嫌だ、絶対離さないからな!誰か!誰か来てくれ〜!」
森口が精一杯の大声を張り上げた時、暗闇に青白い光がバチバチッっと光った。
森口の体が地面へと落ちる。
その男、青柳の手にはスタンガンが光っていた。青柳が歩き出そうとした時、森口の手が青柳の足首を掴んだ。
「な、何なんだこの男は」
と青柳はその手を払いのけようとした。しかし、森口の手は離れなかった。
青柳の足首を掴んだまま、森口は失神していた。
× × ×
宮岡は確かに森口の声が聞こえたように思えた。
松本を廃墟となった製鉄所から救出し、車に乗り込もうとした時である。
「今、声が聞こえなかった?」
「え?、別に聞こえなかったけど」
と藤本が答える。
「誰の声だよ」と富沢。
「麻生君の・・・声が」
と言うやいなや宮岡は運転席に飛び乗った。
「乗って!すぐそばに黒のハコスカが停めてあったの」
そう言って宮岡はアクセルを踏んで、猛スピードで発進させた。
ものの1分でガード下に到着した時、丁度、青柳が森口の手をほどいて車に乗り込むところだった。
「あいつだ。あいつが青柳さんです!」
と早瀬が言った。
「森口さん!」
と藤本が車から飛び降りた。
それと同時に青柳は、ハコスカを発進させた。そのまま宮岡もその後を追う。信号を無視し、右へ左へハンドルを切って逃げる青柳の後を宮岡はぴったりとくっついて走った。
「お前、運転うまいな」
と助手席の富沢が言った。
「乱暴な運転は特にね!」
と言って宮岡は、ハコスカに車を体当たりさせる。それでもハコスカは停まらない。何度かもみあっているうちに、二台は広い道へと出た。
「ルート16だ。ここでとどめよ」
そう言って宮岡はハコスカの横に並び、思いっきりハンドルを左に切った。激しい金属音と共に、ハコスカはガードレールに衝突して、やがて止まった。
富沢と小沢がハコスカへと駆け寄る。運転席の扉が開いて、青柳がふらふらと這い出してきた。富沢が青柳に掴みかかろうとした時、小沢がそれを制した。
「大丈夫だよ、謙ちゃん。もう逃げられないから・・・」
青柳はちらりと小沢を見て、そのまま観念するかのように地面に倒れ込んだ。
× × ×
黄色いテントの中はまるで別世界のようだった。色鮮やかに点滅する照明の中で、若い役者が汗びっしょりで芝居をしている。
客席と呼べるかどうか怪しいような桟敷席に座って、富沢は小沢に聞いた。
「・・・あの時、青柳と何を喋ったんだい」
小沢は一瞬芝居から視線を外して、やがてゆっくりと口を開いた。
「・・・やっぱり謙ちゃんの読み通りだったよ。彼は、別に誘拐するのはトム君じゃなくてもよかったんだ。いや、誘拐する気なんか最初は無かったんだ」
× × ×
 「ご協力、感謝します」 「ご協力、感謝します」
そう言って警官は敬礼をして去っていった。横須賀署の取り調べ室の廊下で富沢と小沢は顔を見合わせた。
「トム君に、何て言ったらいいか・・・」
「あいつは本番に間に合えばそれでいい、とか何とか言うと思うよ。カズさんが気にすることじゃないさ。さ、早く帰ろうぜ」
と小沢の肩を叩いて富沢は歩き出した。
その時、隣の部屋の扉が開いて、警官に連れられて青柳が出てきた。手には手錠が嵌まっている。青柳は警官に促され、顔を伏せたまま小沢の横を通りすぎた。重い空気が廊下に淀んだ。
青柳と警官が廊下の角を曲がろうとした時、
「青柳君」
と叫んで、小沢が駆け寄った。警官が怪訝そうな表情で小沢を見る。
「・・・青柳君」
と口を開いた小沢の言葉を切って、青柳のほうから話し始めた。
「小沢さん、ごめんなさい。本当はこんなこと、するつもりじゃ無かったんです」
「何で、何でこんなことを」
「・・・稽古場で小沢さんと再会した時、あなたは役者で、僕は配達人だった。あなたは今でも自分の道を進んでいて、僕は挫折してた。あなたは僕にこう言いましたよね。仕事頑張ってるんだね、順調なんだねって」
「・・・君がだって、この地域のチームリーダーに選ばれたって言ったから」
「順調でも何でもなかったんですよ。・・・僕も大学を出て、芝居を続けてたんです。でもうまくいかなくて、その時作った借金で首が回らなくなって、借金返すだけの毎日を送ってた。だから本当は芝居をやっているあなたの顔なんか見たくもなかった。けど、仕事だから必ずあの稽古場には配達にいかなきゃならないし、あなたは笑顔で僕に話し掛けてくる。だんだん、今の生活が小沢さんのせいだって思えるようになってきて・・・。この公演がうまくいかなければいいって、本気で思ったんです。そうなるんであれば方法は何だって良かった。あの人を誘拐したのだって、たまたま話に聞いてた松本って人が、あの日、あの大雪の日、電話に出たから」
傍にいた警官がため息をついて言った。
「もういいだろう」
青柳の手錠を持って促す。青柳はまた、うつむいて歩き出した。そして振り返って最後にこう言った。
「本当にごめんなさい。公演の成功を祈ってます・・・」
そういい残して青柳は廊下の闇へと消えていった。
× × ×
「お、謙二さんにカズさんじゃないですか。どこ言ってたんですか」
上石神井の駅の改札を抜け、森口が叫んだ。
「バカ、お前を待ってたんだよ。今日退院したんだろ」
「ええおかげさまで。松本さんとあづさも迎えに来てくれたんですよ」
森口の後ろから笑いながら二人が出てくる。
「あづさに伝言したんだけどな。一人で先走ると痛い目にあうって」
と富沢が言った。
「でも僕のおかげで事件解決じゃないですか」
と誇らしげに語る森口の頭に宮岡のつっこみがパシンと入った。
「この人ね、同じ病室のおばあちゃんに自分は名探偵だ、名誉の負傷だ、って言ってたのよ。挙句の果てに、見舞いに行った私のことを、そのおばあちゃんに僕の秘書だって」
「いいじゃん、少しくらい脚色したって」
「あなたが何を解決したって言うの?車の中でしょっちゅう居眠りしてたくせに」
「そんなこと言ったらあづさだって運転してただけじゃん」
と本気で喧嘩になりそうな二人を見て富沢が割って入った。
「まあとにかく、事件も解決して公演も無事に終わったんだからいいじゃないか」
「そうだね、本当に無事公演を終える事が出来てよかった」
小沢は感慨深げに言った。
「公演終了後の稽古場っていうのは、空気が緩みまくってるからな。いっちょ引き締めなきゃいかんな。本番前のような張り詰めた空気を作らないと」
と松本が言った。その言葉に宮岡が続く。
「さ、行きましょう。稽古場に」
「まずは松本さんが玄関を開けた時に、張り詰めた空気を感じないと駄目だよ」
松本雄介は熱弁した。
「本気でやるの?やめようよ、怒られるよ」
と山田が答える。
「大丈夫だよ、シャレだよ、シャレ」
「シャレになんないって」
稽古場で二人が押し問答をしている時、玄関の外から賑やかな声が聞こえてきた。
「来た。よし、台本どおりな」
と松本雄介が身構える。
 玄関の扉が開く。松本と宮岡達が入ってきた。そこへ松本雄介と山田が走り込んでくる。 玄関の扉が開く。松本と宮岡達が入ってきた。そこへ松本雄介と山田が走り込んでくる。
「松本さん、聞いてください。大変なことになりました」
と松本雄介が息を切らせて言った。
「ん、どうしたんだよ」と松本。
「久間さんが、いなくなったんです。台本書くのに疲れた、って書き置きを残して」
宮岡と富沢が顔を見合わせて呆れた。
「そうか、失踪したか。この稽古場では今回みたいな事件は珍しくなくなるかも知れないな。あ、どっかで聞いたなこの台詞」
と松本は笑いながら稽古場に入っていった。そして振り返って松本雄介に言った。
「雄介。張り詰めた空気が全然作れてないよ。もっと勉強しな、芝居を」
穏やかな春の日差しの中、上石神井の稽古場に、ようやく穏やかな空気が流れていた。
おわり
|