|
第四話 「離れの納戸」
 日曜日の朝七時。西武新宿線、上井草駅からしばらく歩いたところにその集荷センターはある。この業界も競争が激しく、翌日お届け、時間帯お届け、日曜祝日お届けといった新サービスでシェアを争っていた。この会社は大手ではないものの、右へ習えでその全てのサービスを導入していた。 日曜日の朝七時。西武新宿線、上井草駅からしばらく歩いたところにその集荷センターはある。この業界も競争が激しく、翌日お届け、時間帯お届け、日曜祝日お届けといった新サービスでシェアを争っていた。この会社は大手ではないものの、右へ習えでその全てのサービスを導入していた。
「日曜日の早番なんて、最悪だ・・・」
新人ドライバーの早瀬は、眠い目をこすりながら集荷場に向かった。ホームと呼ばれるトラックを付けるスペースに、早くも時間指定、曜日指定のシールの貼られた荷物が山積みになっている。
「ラララン、ラララの宅急便♪一歩前へ・・・」
と言いながらも、膨大な荷物を前にして早瀬の足は動こうとしない。とりあえずコーヒー、と頭の中は早くも逃げ腰になっている。
「お前いつになったらあの狭いルートの道を覚えるんだよ。指定された時間に遅れるくらいなら、早めに届けたほうがマシだ。とっとと荷物積んで出発しろ」
そんな早瀬に業を煮やして、でっぷり太った上司が小言を言いながら歩いてきた。
「本物のドライバーはな、自分のルートにある家と名前を全部覚えるんだ。この角の家が鈴木さん、となりは佐藤さんって具合にな。そこまでして初めて一人前の・・・」
早瀬は長くなりそうな上司の説教を聞き流して、荷物の積み込みを始めていた。
「現場に戻って、少しダイエットすればいいのに・・・」
早瀬は、絶対に上司に聞こえないように呟いた。しかし、積んでも積んでも荷物の山は減る気配はなく、上司の前でもあからさまに辛い表情が出てしまっている。
「いくらなんでも、日曜の朝っぱらから何でこんなに・・・」
呟いたつもりが、今度は上司に聞こえてしまっていた。
「馬鹿野朗、気合だよ気合い。でも安心しろ、大口があるんだよ。五十個口」
「ごじゅっこ、ぐち?」
そんなに大口はめったにあるものではない。
「お前、このルートについて一月も経ったんなら、あそこはもう覚えただろ」
「何をですか」
「鈴木さんや佐藤さんじゃ、お前の頭じゃまだ当分かかりそうだけどな。その名前は覚えやすいぞ。宛先見てみな」
よく見ると荷物の山の半分は、同じ形に梱包されたものが五十個積み上げられて出来たものだった。早瀬は荷札を確認した。
「練馬区石神井台・・・・劇団6番シード」
× × ×
「それにしても、すがすがしい朝ですね。昨日の嵐が信じられませんよ」
国道16号線を東京方面に向かいながら、助手席で菓子パンをかじりながら森口が言った。
「どこがすがすがしいのよ。それにいつ嵐がきたのよ」
運転もしないで気楽なもんだ、と宮岡は朝から気分が滅入っていた。
「台本の台詞だよ、敷島の。でもほらすがすがしいのは本当だね」
「どこが。昨日一日、五井町の旅館から役場からファミレスまで駈けずり回って、何の情報も得ることが出来なかったのよ。おまけにこんな狭い車で一夜を明かして・・・」
「でも本番が近づくと台本の台詞を使ったギャグとか稽古場で流行るよね。日常会話に織り交ぜてみたり」
そうだ、本番は近づいている。こうして捜索の旅に出ている以上、何かしらの手がかりを得たい、宮岡はもう一度頭の中を整理してみた。
「・・・確かに、もしあのニュースに映っていたのがトム君だったとしても、五井町に滞在している形跡は無い。ただ単に五井町を通過しただけなら・・・聞き込みをしてすぐに手がかりを得られるほうがよっぽど奇跡だわ」
「五井町からそのまま16号線を突っ走ったら、東京湾をぐるっと回って房総半島の先っちょに出るね」
森口が地図を見ながら言った。
「トム君はどこに向かってたのかしら」
「ねえ、松本さんは運転してないんじゃない」
一人うまそうに菓子パンをほおばりながら、森口が尋ねる。
「何で」
「だってさ、あのビデオに映ってた人、助手席に座ってたよ」
「・・・そうだ、肝心なことを見落としてた。オレンジ色の服を着た男がトム君かどうかだけに気を取られて」
「他に運転してた人がいるって可能性のほうが高いね」
「誰かとどこかに向かってた。または・・・」
「誰かにどこかに連れ去られてた」
「変なこと言わないでよ」
そう言いながらも宮岡は、完全に否定することは出来なかった。だとしたら・・・誘拐?それなら相手からの連絡があるはず・・・。
「ねえ、今どこに向かっているの」
森口は地図をペラペラとめくりながら尋ねた。
「手ぶらで稽古場には帰れないわ。五井とか、井沢とかが付く町名って関東だけでも二十くらいあるの。それを・・・」
「全部回るの?」
宮岡は答えられなかった。手がかりは欲しい。でもそれを探すすべが見つからない。勿論、そんな町を回ったところでどうにかなるとも思っていなかった。房総半島のほうに引き返そうかと思った時、
「ねえ、16号線って横浜までつながってるんだね」
と森口が言った。
「そうよ、大きな環状線みたいなものね」
「だったらさ、横浜行こうよ」
「どうして」
「松本さん、こないだまで横浜に住んでただろ。何か手がかりが得られるかもだよ。俺、前に住んでた家に行ったことあるし」
確かに、このままではらちが開かない。宮岡は、珍しく森口の提案に乗ってみることにした。
「そうね、行ってみましょう。横浜に」
× × ×
「こんにちはー。宅急便でーす」
日曜日の午前中にお届け。午前十一時半。早瀬は指定どおりの時間に到着してほっとしていた。以前配達した時のことを、さすがに早瀬も覚えていたのだった。
「劇団の稽古場か」
中で稽古中の声が聞こえてくる。気になって玄関から覗きこんだ時、
「ごくろうさまです」
と、稽古着の宇佐木が現れた。
「ええと、五十個口の荷物なんですけど・・・」
「え、ちょっと待ってください」
そういって宇佐木は奥へ消えていく。とりあえず、運びこんで終わらせようと、早瀬は荷物を取りに行った。
運び終わって、さすがに早瀬も息を切らせている。結構な重さだった。男手がリレーのように荷物を奥へ運んでいる。
「あの・・・、これは何が入っているんですか」
滅多にない五十個口の中身が気になって尋ねる。
「これは、チラシですよ」
と藤本が答える。
「チラシ?どうりで重いはずですね。でも何のチラシですか」
「次回公演のチラシです」
と言って藤本は運んでいた荷物を降ろして封を開け、チラシを取り出した。
「サスペンスお好きですか?是非観に来てくださいよ」
しっかりと営業も忘れない藤本の後ろで、荷物を運びながら小沢が加勢する。
「そのチラシに映っている手、それ僕なんですよ」
「だから何なんスか」
笑いながら二人は稽古場の奥に消えていく。早瀬の手に残ったチラシには、鞄を持った男と、桐の林らしき背景がオーバーラップしている写真が載っている。早瀬はチラシの中心に書かれた短い文章に目が止まった。
「これって、キャッチコピーってやつだよな。どういう意味なんだろ・・・」
「あの」
その声に我に返って顔を上げると、宇佐木が立っていた。
「はい」
「あの、ちょっとお聞きしたいんですが・・・」
「どうぞ、何なりと」
「あの、ちょっと前の日曜日も配達にいらっしゃいましたよね。ほら、あの大雪の日」
「え、ああそういえば」
確かに、あの大雪の中チェーンをつけて配達していたことはよく覚えていた。
「確か、午後二時頃にいらっしゃいましたよね」
時間帯お届けをはるかに過ぎて届けた、早瀬ははっきりと覚えていた。
「ええ、劇団6番シードさんに、荷物があったと思いますが。それが・・・」
「いえ・・・あの日、何か変わったこと、ありませんでした?」
「え」
「何でもいいんです。何か不審な人がこの家のそばに立っていたとか、配達の時に誰かとすれ違ったとか」
「急に言われてもなあ・・・何かあったんですか」
「何か覚えてませんか」
あまりに宇佐木が熱心に聞いてくるので、早瀬も記憶を隅をほじくり返してみた。あの大雪の日、もうこの仕事にうんざりして・・・。
「あ、そういえば」
「何か、あったんですか」
「いや、何があったって訳ではないんですが。あの、いつもこの家の脇の塀に車を停めて、よく一服するんです。ほら、道幅も結構あるんで。そこに車がずっと停まってていらいらしたのを覚えてますね。いやあ、配達の車ってデカいでしょ、なかなか停めるとこが無いんですよ」
「家の脇に・・・。それは何時くらいですか」
「どうですかね。二時に配達して、その時にもう止まってましたから。その後ぐるっと回ってまた来た時はもう無かったから、三時くらいまでですかね」
「それはどんな車ですか」
「はっきり覚えてますよ。一面雪景色の中、黒い車体が目立ってましたから。それにね・・・」
「それに?」
「昔憧れてた車だったんですよ。ハコスカって言って、古い形のスカイラインです。今じゃなかなか見かけませんよ」
× × ×
 宮岡と森口が松本が以前住んでいた横浜の家に着いたのは、もう日が暮れかかった頃だった。 宮岡と森口が松本が以前住んでいた横浜の家に着いたのは、もう日が暮れかかった頃だった。
「宮岡さン、元気ないずら。・・・難しいなあ、方言も」
森口が台本に出てくる使用人辰哉の言葉でこの道中喋り続けていたので、宮岡はぐったりとしていた。あんたのせいよ、と喉まで出かかったが言葉にする気力も無かった。この二日間で何百キロ運転しただろう。
「宮岡さンは、機嫌が悪ぃだな」
「とにかく、車を降りましょう」
そういって宮岡は、一軒家であるその家に向かって歩き始めた。以前松本は友人と一軒家を借りて共同生活をしていたということを道すがら森口に聞いていた。
その家は完全に雨戸も締め切っていて、まだ借り手が見つかってない様子だった。宮岡が玄関の扉を回す。当然鍵がかかっている。
「案外ここに監禁されてたりして」
「馬鹿」
庭に回ってみる。朽ちた物干し台と物置。そして車一台やっと停めることの出来る駐車スペース。それ以外には何も無かった。
「離れの納戸でも調べてみるか」
「物置のこと?」
「台本の台詞的に言うと、離れの納戸。ちなみに下坂の台詞ね」
「はいはい」
もう日が落ちようとしている。疲れた意識の中で宮岡は、横浜に来た事、もっと言えば以前松本が住んでいた家に来たことを後悔した。こんなことをしていても、いたずらに時間が過ぎていくだけだ。今日も何の収穫も無かったことがたまらなく悔しかった。
「あんたら、松本君の知り合いかい」
突然の声に、二人はどこから聞こえてきたのか一瞬分からなかった。向かいの家の庭に人のよさそうなおばさんが立っているが見える。
「はい、そうですけど」
と宮岡。 おばさんは、いそいそと庭から這い出るようにしてやって来た。
「あの、引越しの時にさ、残ったゴミは処分してあげるっていったんだけど、捨てていいものかどうか分かんないものがあってね。ちょっと見てくれないかい」
そう言っておばさんは、物置を指さした。
「任せてください」
と森口は物置へ向かう。重い錆びた扉を開けると、埃の被った木材やブルーシートなどが置いてある。
「こうなったら独自の調査に踏み切るしか無いと思ってね、離れの納戸あたりから調べてみたんだよ」
と下坂の台詞を引用しながら物置をあさっていく森口。少し下がった埃の被らない位置で宮岡も見守っていた。
「ん、何だコリャ」
と森口が奥から一枚の板をひっぱり出す。その板は直径50〜60センチに丸く切られていて、赤地に黒い二本線が塗料で塗られている。
それを見た瞬間、二人の表情は氷りついた。
「何だい、何かお宝でも見つけたのかい」
とおばさんが覗き込む。
「そっだらこと偶然だべ、そっだらこと・・・」
辰哉の台詞を引用した森口の顔にも笑顔は無かった。宮岡は、松本が台本に書き残した言葉を思わず口にしそうになった。二人の尋常ではない表情を、おばさんは不思議そうに見つめている。
その赤く塗られた丸い板には、「バス」という文字と「五井沢行き」という文字が書かれていた。
「そうよ・・・単なる、偶然よ」
× × ×
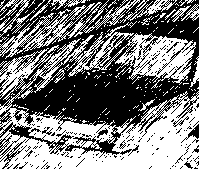 「これは・・・偶然じゃないよね」 「これは・・・偶然じゃないよね」
パソコンで拡大された映像を見て、稽古場で宇佐木は呟いた。
「うん、偶然じゃないと、思う」
藤本はそう言って画面をもう少し拡大した。例のビデオ映像である。リポーターが喋っている後ろに偶然映っていた車。「6」というプリントの入ったオレンジの服を着た男が助手席に座っている車。
それは黒いスカイラインだった・・・。
つづく
|