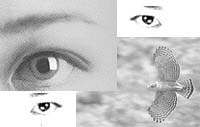
彼こそが希望の星の・・・ |
崎山は歩いていた。日曜の朝だからなのか、街はひっそりとしている。雲行きが怪しい。そういえば昨日のニュースで関東・甲信越地方が梅雨入りしたと言ってたな、一瞬空を見上げて崎山は思った。
崎山が向かっているのはとある劇団の事務所だ。たしか地図だとこの辺のはずなんだがな。崎山はきょろきょろと辺りを見回しながら歩きつづけていた。やがてぽつぽつと雨が降り始めた。来る途中に前もって買っておいた傘をさそうとした時、崎山の目に小さな看板が飛び込んできた。
「劇団特売シート」
お、ここだ、とさしかけた傘を丁寧にたたみ、看板の横にあるドアホンをゆっくりと押した。はーい、という元気のいい返事の後に、ばたばたとドアの方へ駆け寄ってくる足音が聞こえた。
ここのところ、崎山は芝居について深く考えるようになっていた。長い業界生活でこんなにも本気で芝居について考えたのはこれが初めてのことだった。今まではただなんとなく、顔が良いからとか早口言葉ができるからと言った安易な理由でタレントを抱え込んできたが、それは不埒なことだと気付き始めていた。オレに足りなかったのは人を見る力だな、と深く反省していた。それ以来、崎山はあらゆる劇団の公演を見に行くようになった。いろんな芝居を見て、いろんな役者を見て目を肥やしていこう、と。長い業界生活でこんなにも本気で芝居を見るのはやはりこれが初めてのことだった。
劇団にもいろんなカラーがある。とにかく2時間笑わされっぱなしの芝居を見せるところや、異常にテーマが重くて見ると生きていくのが辛くなるようなところ、舞台美術は一流なのに、芝居はというと小学校の学芸会のようなところ、いかにも舞台っぽい大げさな芝居をみせるところや、リアリティのある自然な芝居をしながらも心に訴えかけてくるところ…好き嫌いは抜きにして、本当に多種多様である。そうした数ある劇団の中で崎山が目をつけたのが、この「劇団特売シート」だった。
練馬区の閑静な住宅街のなかに特売シートの稽古場は建っていた。立派な一軒家だ。劇団発足の時、稽古場を借りるお金が無く、ホームセンターで特売していたブルーシートを公園に敷いて稽古を始めたというのが名前の由来なんですよ、と主宰者の浜田は崎山にお茶を振舞いながら笑った。
「今ではこんなに立派な稽古場を持っていますけど、昔はそりゃあもう大変でした。小劇団の宿命って奴ですかね、お金がなくて。あ、お金は今も無いんですけど」
特売シートの芝居は実にストーリーがはっきりしていて分かりやすい。自然に笑ったり泣いたりできる物語を見せてくれる劇団だ。見終わった後になんともいえない懐かしい気分にさせられる。とても、温かい劇団だ。
「もっとたくさんの人にいい物語を届けたい、と言うのが私たちの願いです。うちの芝居を見て少しでも生きる力や希望を持ってもらえたら、これほど嬉しいことはありませんね」
浜田は少年のような生き生きとした目で語る。これぞ芝居の真骨頂だ。崎山は自分の中途半端さに情けなさを感じ始めていた。
「今、うちの事務所で育てていく俳優を発掘しているところなんです。こちらの劇団にはいい役者さんが揃っているような気がしてこうしてやって来たんですが」
崎山はお茶をすすりながら今日ここへやってきた理由を簡単に説明した。浜田は、まあゆっくり稽古でも見ていってください、と稽古場の方へ案内してくれた。
劇団員達の年齢層は実に幅広い。崎山と同じぐらいの中年男性もいれば、まだ大学生の若者もいる。だが、そんな年齢の差など微塵にも感じさせない程、全員が輝いているように崎山の目には映った。同時に、自分も芝居に携わっていく人間として誇りを持てるようになりたい、と強く感じていた。
崎山はふと、稽古場の隅で熱心に稽古の様子を見ている青年に気付いた。その視線は誰よりも熱い。眉間にしわを寄せた、どんな台詞も聞き逃さないぞという感じの獲物を捕らえるような目つきに、崎山の興味はかられた。和やかに、でも厳しく続いていく稽古から、彼は一時も目を離さない。崎山は確信した。彼の目こそ、真の役者が持つ目だ。どの劇団の芝居を見ても、本当に上手い役者は同じ目をしていたな。今はまだ輝きは鈍いけれど、きっと磨けば光るはずだ。こういうダイヤモンドの原石を自分で見つけ出すために、オレは今日までいくつもの芝居を見てきたんだからな。崎山の心にメラメラと赤い炎が燃え始めた。
「彼の名前はなんと言うんですか?」
コーヒーを片手に、休憩室がわりのリビングで休んでいる浜田に崎山は尋ねた。
「ああ、彼ね。松本雄介です。まだ22なんだけど、彼は本当によくやってくれますよ」
稽古中の熱いまなざしは消え、まるでこどものように劇団員達とはしゃぐ松本を見ながら浜田は言った。
「器用なんですかねえ。よく気が利くし。男のくせにちょっと細かいところがあるんですが、彼がいないとうちの劇団も困るんですよねえ」
その言葉を聞き、やはりオレの目に狂いは無かったな、と崎山は誇らしい気持ちでいっぱいだった。間違いない。彼こそがオレの希望の星だ。
短い休憩時間が終わり、稽古が再開された。休憩時間に緩んでいた空気はもう何処にも存在しない。ぴんと張り詰めた緊張が稽古場を包んでいた。ふと回りを見渡すと、さっきまで片隅で真剣に稽古を見ていた松本と言う青年がいない。おかしいな、何処に行ったのだろう?ああそうか、分かったぞ、きっと別の部屋で一人、稽古をしているんだな。やはりできる奴は違うな、と崎山は一人で感心していた。ぜひ松本と言う青年と話がしたいと崎山は思ったが、とても稽古場を抜けられるような空気ではなかった。それからノンストップで続いた2時間の稽古中崎山は、松本をどうやって育て、どうやって売り出すか、にやけた笑顔を隠すこともなくそんなことばかりを頭の中に駆け巡らせていた。
「おつかれさまでした〜!」
午前中の稽古が終わった。どやどやと劇団員達は休憩室になだれ込んでいく。みんなに付いて崎山も休憩室に入っていく。するとそこにはエプロン姿でご飯をよそっている松本がいた。
「今日のメニューは鶏のから揚げ、大根の味噌汁にさっぱり仕上げのツナサラダですよ」
松本は手際よく食卓におかずを並べていく。
「うちはねえ、この炊出しが自慢なんですよ。松本は男のくせに料理が上手くてねえ。いつもお昼には細かくカロリー計算までしてご飯を作ってくれるんですよ。3時には手作りおやつまで出てくるし。気が利くでしょう?いや〜、松本がいないとうちの劇団員たちは栄養失調になっちゃうよ」
浜田はけたけたと笑いながら言った。
「稽古中もね、稽古そっちのけでいっつも献立ばっかり考えてるんですよ。稽古中、眉間にしわを寄せてたら、それはカロリー計算してる時なんですけどね」
「え、じゃあ彼は役者じゃなくて…」
「ええ、お手伝いさんです。松本はきっといい主夫になりますよ〜」
いい主夫か…あの熱い視線の先には鶏のから揚げが揺らめいていたんだろうな…途方に暮れる崎山に気付いたのか、松本は崎山に駆け寄り、とびきりの笑顔で言った。
「今日のご飯は自信作なんっすよ。崎山さんも食べてってくださいよ」
笑顔にならない笑顔を見せ、小さく首を振り、崎山はその場を立ち去った。
これじゃあ、うちの米倉が作るコントよりはるかにおもしろいオチだよ。笑わせてくれるよ。真実なんて、知るもんじゃないな。彼こそが希望の星のはずだったのにな…
強くなり始めた雨に打たれながら、自分の見る目が無かったという真実に、崎山はまだ気付いていなかった。
つづく |